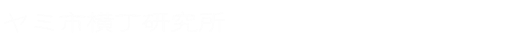そもそもヤミ市研究は私がハモニカ横丁に関心を持ち始めたときの二〇〇四年頃といえば全く盛んではなかった。一九八〇年頃に社会学者の松平誠(立教大学)がヤミ市に関する著書を二冊ほど出しているだけで、そのあとはまとまった研究成果はなかったが、二〇〇三年に東京大学の初田香成が修士論文で「戦後東京におけるバラック飲み屋街の形成と展開」という論文を建築学会の論文集に投稿していて、掲載から一年後に自分と同じように関心を抱いている人がいることを奇遇に思うとともに、大変心強く思えた。しかし、当時学部三年生の自分は東京大学博士課程に在籍する先輩にいきなりコンタクトをとれることもなく、いずれお会い出来たら程度に思っていた。また、自分が気づくのが遅れてしまったが、二〇〇二年一二月には、藤木TDCとブラボー川上による「まぼろし闇市をゆく 東京裏路地懐食紀行」(ミリオン出版)が出版されており、好評で度々重版され、のちのち文庫にもなり(二〇〇六年二月、ちくま文庫)、さらには続編まで出る(二〇〇八年四月)という盛況ぶりだった。
大学三年生の頃はなんの成果もあげていなかったが、丁度その頃大学の授業でホームページを作成する授業があり、多少HTMLのタグの知識を手に入れたので、ヤミ市横丁研究所というホームページを立ち上げ、ヤミ市を起源とする横丁について調査しているとを掲示した。全部で一〇〇字くらいしか書かれていないだろう、簡素なホームページだった。
しかし、そんな質素なデザインのホームページではあったが、大学三年生の最後の方でレポートをまとめたことをネット上で公表すると、ホームページにアクセスが増え始め、レポートを見せてくれと、大衆食に関する著書が多数ある遠藤哲夫と、当時一橋大学大学院で博士論文を執筆中だった五十嵐泰正(現・筑波大学大学院准教授)が関心があるということでいち早く連絡をいただけ、度々ヤミ市研究に関する助言をいただけた。
その後、二〇〇六年四月に就職して間もなく、卒論に関する問い合わせを初田香成からいただき、会わないまでも連絡を取り合うようになった。その後も度々卒論に関する問い合わせをもらったので、ハモニカ横丁の商店主の方から抜粋して小冊子にしてはどうかと連絡をいただいた。卒論自体の完成度はけして高くはなく、評価されるものではなく見るに堪えないものだったので、卒論を誰にもお見せできなかったということもあり、社会人一年目のときに要約して人様にお見せできる状態にして大量に印刷して安価で販売することにした。この印刷には最初、〇〇万という金額がかかったが、多くを干物店なぎさやの店主・入沢勝が男気で出してくださって実現した。
しかし、そんな冊子を毎日のアクセス数が一〇件程度のホームページで販売してもまったく売れるわけもなく、印刷してから一か月での販売部数は三冊という緊急事態だった。しかもその三冊は、横丁に酔客に対する押し売りということで売れたというよりは、買ってもらったと表現すべきものだったと思う。
ところが一気に追い風が吹く。武蔵野市役所のまちづくり関係の部署にいた方が市長の定例会見でたまたま来庁していた朝日新聞記者に小冊子の存在を伝えてくださり、同紙の東京都内版で大きく記事になった。するととてつもない数の注文メールを受信した。朝起きると一〇通くらい入っていて、夜、会社から帰ると四〇通くらい来ていた。それから一週間くらいは毎日かなりのメールをいただき返信には三日~一週間ほど遅れで対応せざるを得ない状態だった。
ヤミ市研究について ヤミ市横丁研究所
![]()