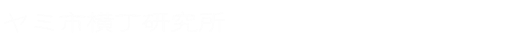第1回 仙台市長町 「2番街」
![]()
仙台駅から南に電車で1駅(4分)、長町にある穴場的横丁「2番街」を調査してきた。
長町駅は地下鉄ということもあり、地上には駅前広場がなく、
周囲には片側2車線の太い道路(国道4号線)が走り、
車の交通量も多いことから、郊外らしい街並みが続く。
車の交通量が多く、歩く人の数もまばらな国道4号線沿いに2番街の入口の看板がある。
2番街と書かれた看板の他に「長町マーケット」と書かれた看板もあった。
以前は「長町マーケット」と呼ばれていたが、
あるときから「2番街」へと改名されたようだ。
内部に足を踏み入れると、
飲み屋街であることがすぐにわかった。9割は飲み屋。
この飲み屋街の中に唯一、一般の商店を見つけることができた。
「鈴木はきもの店」だ。
店主の鈴木フヂエさんは昭和25年3月からここで商売を営む、2番街の最古参。
鈴木さんから2番街の形成過程についてお話を伺うことができた。
2番街一帯には終戦直後からヤミ市が形成された。
当時は簡易的な店舗が並んでいたが、昭和25年に現在の形となった。
戦後、2番街一帯の土地は、
天賞酒造(仙台市八幡町29)の天江勘兵衛氏が所有しており、
その近くで営業していた材木店が土地を借り、マーケットを造った。
そのときは引揚者が多く入ってきたようだ。
昭和50年代に鈴木さんの旦那さんが中心となり、
土地の所有者である天江氏と交渉を行い、土地の権利が委譲され、
現在2番街一帯には30名前後の地権者がいる。
今でこそ、2番街にある店の9割は飲み屋となっているが、
戦後形成されてから長い間、
豆腐屋、煎餅屋、うどん屋、魚屋などの一般商店が多く連なる商店街であった。
その頃は1階が商店、2階が住居となっていたこともあり、
2番街には子供達の遊ぶ姿が多く見られた。
特に七夕のときなどは、街を挙げて至る所に装飾を施し、
大きなイベントとして大変賑わった。
ところが近所に大型スーパーができると、
2番街の客は激減。その頃から商店は次々と姿を消し、
入れ替わるように飲み屋が次々と出店し、現在のように盛り場化していった。
飲み屋が増えたせいか、ガス・水道などのインフラの整備が急務となった。
終戦間もない頃に形成された2番街一帯に敷設された
ガス管・給水管は埋設深さが浅く、管径も小さかった。
そういったこともあり、ガス管は至る所で漏れ、
いつ火事になってもおかしくない状態であった。
そこで、2010年にガス管を本管から再度やり直し、
2番街一帯のガス管は全て更新された。
今回、お話を伺った鈴木さんは、
こういった2番街の整備へ向けて行政などに働きかけをするなど、
まちづくりの中心として尽力され、
商店の内部にはその功績を讃える賞状などが飾られていた。
ぜひ、これからもお元気で2番街を支えていただきたい。
調査のスケジュールの関係で今回は昼間に訪れたが、
ぜひ次回は夜に訪れたい。